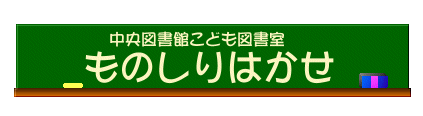
このコーナーでは 図書館のしくみを すこしずつしょうかいするよ!
みんなも 図書館ものしりはかせをめざそう!
(2009年 5-6月号 より)
今回のものしりはかせは、
本
〜紙がなかった時代には〜
図書館にはたくさんの本があります。 絵本や小説、地図やずかんなど、大きさやページ数はさまざまですが、 文や絵がかかれている、たくさんの「紙」をひとつにしたものを、 わたしたちは「本」とよんでいます。  「紙」は、わたしたちのまわりにたくさんあるので、 「本」が「紙」でできていることは、あたりまえと思ってしまいますね。 では、大むかし「紙」がなかった時代には、「本」もなかったのでしょうか。 今回は、ものしりオバケちゃん  が、「本」がいつごろ、どんなかたちで作られたのか、
が、「本」がいつごろ、どんなかたちで作られたのか、しょうかいしてくれます。 |
|
|
||||||||||
|
|

 |
|
||||||||
|
|
|
|
||
|
|
 草でつくられた本
草でつくられた本
古代エジプトでは、文字をきろくするためのパピルスを作りました。 パピルスは、パピルスという植物のくきから作られます。 〜パピルスのつくりかた〜 1.パピルスのくきの皮をむく。 2.うちがわのやわらかいぶぶん(「ずい」といいます)をうすくさく。 3.「ずい」をローラーでおしのばし、ほそながくして水につける。 4.水につけた「ずい」を、たてよこにかさねてならべる。 5.ぬのにはさんで、おもしをかけて、かわかす。 パピルスは、おりまげによわいので、今の「本」のように、とじるのにはむきませんでした。 そこで、なんまいもつなぎあわせて、長い巻き物のかたちをした「本」ができました。 長さ4メートルのものもあるんだって。 英語で紙のことをペーパーといいますが、これは5000年も前の紙「パピルス」からきている言葉だといわれています。 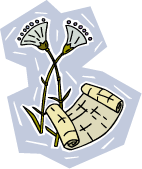  |
|
|
|
|
|
||
|
|
 ねんどでつくられた本
ねんどでつくられた本
メソポタミアでは、ねんどで本をつくりました。 ※メソポタミア・・・ギリシャ語で「2つの川にはさまれた土地」といういみで、ほぼ、今のイラクの国にあたります。 〜ねんどの本ができるまで〜 1.メソポタミアの土地には、大きな川が流れています。 2.上流からこまかい土がはこばれ、ねんどの層(そう)が作られます。 3.そのねんどに、今から5000年ほど前から、絵文字がきざまれるようになりました。 4.文字をきざんだら、しぜんにかわくのを待ちます。 大事なものは窯(かま)でやいて、かたく丈夫にして保存しました。 メソポタミアの人たちは、やわらかいねんどの板に、アシのくきを三角形に切って作ったペン先で文字をきざみました。 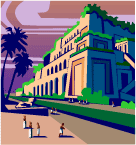  |
|
|
|
|
|
||
|
|
 皮にかかれた本
皮にかかれた本
エジプトで作られたパピルス(紙)の作り方が広まり、たくさん作られるようになったので、材料となるパピルスが、 たりなくなってしまいました。そこで新しく「本」の材料に使ったのが、ヒツジやヤギの皮からつくる、羊皮紙(ようひし)です 〜羊皮紙(ようひし)のつくりかた〜 1.皮をきれいな水であらう。 2.石灰水(せっかいすい)に10日間くらいつける。 3.取り出して、うらおもてに残っている毛や肉をきれいに取る。 4.もう一度、石灰水(せっかいすい)につける。 5.それを木のわくに張り、かわかし、チョークの粉をかけ、かる石でなめらかにする。 動物の皮はうらおもてに書けるし、おりたたむこともできるし、巻くこともできるので、今と同じ「本」のかたちにも、 巻き物にもちょうどよい材料となりました。また、なめらかで、こまかい絵やもようを書くのにもぴったりでした。 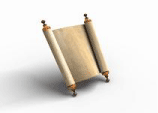  |
|
|
|
|
|
||
|
|
 木の葉にかかれた本
木の葉にかかれた本
インド、スリランカ、タイなどの国では、ヤシの木の葉に文字や絵を書きました。 〜木の葉の本ができるまで〜 1.ヤシの葉の、はばの広いところを使って、同じ大きさに切る。 2.なんまいも重ねて、真ん中にあけた穴にひもを通して、つづりあわせる。 3.いちばん上と下に、板でできた表紙をつける。 498枚のヤシの葉を重ねて作られた「本」もあるんだって。 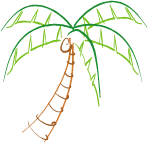  |
|
|
|
|
|
||
|
|
 木のふだにかかれた本
木のふだにかかれた本
中国では、今から3000年以上前に、ウシの骨やカメのこうら、銅など、多くのものに文字や絵を書いていました。 その中でも気軽に使ったのは、木や竹の「ふだ」です。 このふだは、ほそ長い板で、1枚に1行ずつ文章を書きました。 長い文章は、なんまいものふだを、ひもであんで、まとめて「本」にしました。 しかし、木の板でできた「本」は重くてかさばります。 たくさんあると、おき場所にもこまります。 持ち運びもたいへんでした。 それをなんとかしようとして「紙」が発明されたといわれています。 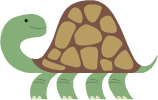  |
|
|
|
|
|
||||||
|
|


|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
 〜紙のつくりかた〜
〜紙のつくりかた〜
1.麻くず、魚のあみ、ぼろ布や植物の皮などの材料を水によくひたし、あらう。 2.こまかく切りきざむ。 3.焼いた草木の灰を入れて、灰汁(あく)をつくり、切りきざんだ材料をつける。 4.灰汁(あく)につけた材料を煮る。 5.煮た材料を水あらいする。 6.うすでつき、さらに水あらいする。 7.どろどろになったものを、竹のすのこですくいとる。(紙をすく) 8.すいた紙の水分をとり、かわかす。 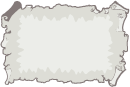  |
|
|
|
|
|
||||||
|
|

辻村 益朗 作 福音館書店 「知」のビジュアル百科 「文字と書の歴史」 カレン・ブルックフィールド 著者 浅葉 克己 日本語版監修 あすなろ書房 「紙」の大研究1 「紙の歴史」 丸尾 敏雄 監修 樋口 清美 構成・文 岩崎書店  |
|
||||
|
|
[ものしりはかせバックナンバー一覧に戻る]
